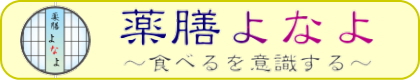薬膳とは?

~空腹と心を満たして、健康維持や美容
病氣の予防、治療にも役立つバランスのとれた美味しい食事~
治療の意味合いである「薬」と 食事や料理の意味合いである「膳」が合わさった
病の治療や改善、予防、美容、健康を維持するための料理のことです。
漢方の起源である、中国伝統医学の基礎理論をベースに
個々の体質や症状、季節、環境などに合わせて食材を選び、レシピをつくる
オーダーメードの料理が基本です。
「身体には良さそうだけど薬臭い?」
「特殊な食材や生薬を混ぜないとダメ?」
「美味しくなさそう。。。」などのイメージをされる方も多いようですが
目的に合わせて、身近な食材でも薬膳はつくることができます。
漢方の起源である予防医学
中国伝統医学は二千年あまりの歴史があり
病氣の治療だけでなく
季節や環境に合わせ、心身のバランスを安定させて病氣や老化の予防をして
健康でよりよい生活を送ることを目的にした予防医学でもあります。
日本には平安時代に遣唐使や僧侶によりもたらされ、
その後、日本の風土や民族に合わせて発展した日本伝統医学(漢方)でもあります。
長寿への願い
時代が変わっても、誰もが健康で長生きしたいと願っているはず。
「生きるためにはどうするか? 」「どう生を養うか?」
今よりも自然界と密接だった先人たち。
彼らの長年の経験から得た知恵は「医食同源、薬食同源」とする食事だけではなく、
運動や精神鍛練、生活習慣、環境などと多岐にわたる分野で治療や養生法としてあります。
そのベースには、「人は自然界の一部であって小宇宙である」「健康とは心と体のバランスが重要である」ということがうかがえ、この教えは、私たち日本人の中にも根づいていると思います。
伝統和食にも薬膳要素がふんだん!!
私たち日本人が季節や風土に合わせて病氣予防や健康維持にと受け継がれてきた和食。
その中には薬膳理論が根付いているものも少なくありません。
お刺身には、大根と青シソ、山葵、菊、が添えられていますがこちらも立派な薬膳なのです。
では、はたらきをみてみましょう。
【例】目的:生魚を食することはリスクが高い!
対策:薬味を添える
- 青シソは腐敗や抗菌作用によって魚毒による中毒を避ける
- 大根は消化を助ける
- 菊は強い抗菌作用をもって解毒、消炎、鎮痛をはかる
- 山葵は解毒と生魚を食すことで冷える胃腸を温める
- 醤油は解毒、食中毒を防ぐ。食材のうまみを引き出し食欲を促す
そんな総合的なはたらきでカラダが危険にならないように防御しているのです。
ここに温かいご飯や日本酒があるとカラダの冷えがより軽減されますね。
ただの飾りとして菊があるのではなく意味がある。。。
あまりにもアタリマエのことで、目を向けていなかっただけだと知りました。
これを機に伝統食にも目を向けながら、薬膳の知恵を食卓に取り入れてみませんか?
組合せの謎が解けるかもしれません。
◆自分を知ろう!食材を知ろう!季節を知ろう!
薬膳の考えを取り入れて食事つくるには、基礎理論と食材の持っている性質や味を知るとともに、
季節や環境、自分の体質を知ることも必要です。
さぁ!感覚をとぎすまし、ご自分に興味を持ちましょう~♪
EM↑
特殊なひとつの菌ではなく、乳酸菌や酵母、光合成細菌など、どこにでもいる微生物で、人間にとっていい働きをしてくれる微生物の集まりです。
乳酸菌や酵母など人にも環境にもやさしい微生物たちの共生体です。
その微生物たちを環境に入れることで、もともとそこで暮らす微生物たちのバランスを整え、豊かな生態系を生み出します。